ウメ 二月の梅
好文木、君の名はウメ

花の文化園の梅園入口
ちょっとなまめかしいww(これは3月の写真)
梅園内
の梅は、「130品種300本」あるとか。⇒昨年の2月の頁再掲

 ウメ 梅
ウメ 梅 
学名:Prumus mume Sieb.et Zucc.
英名: Japanese apricot
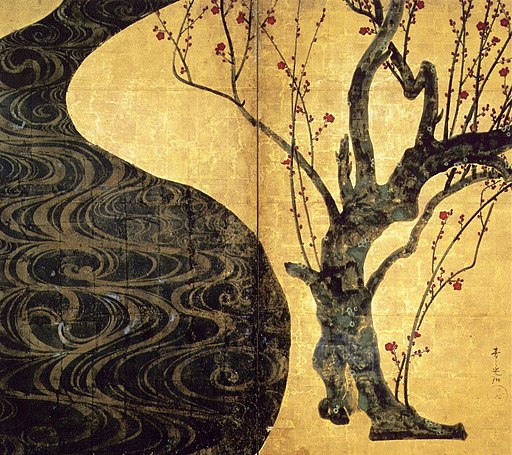 静岡県熱海市のMOA MUSEUM OF ART所蔵名品……紅白梅図屏風
静岡県熱海市のMOA MUSEUM OF ART所蔵名品……紅白梅図屏風MOA 美術館蔵 2004年東京文化財研究所との科学調査により
大きな反響をよんだ尾形光琳筆 国宝「紅白梅図屏風」
(金地の謎)
時代: 江戸時代(18世紀) サイズ: 各 156.0×172.2㎝
素材・技法: 紙本金地著色 二曲一双

尾形光琳 《紅白梅図屏風》
毎年2月に展示しているというが、今サイトで凄い画像をデジタル公開中!
MOA 美術館 https://www.moaart.or.jp/
"光琳が宗達に私淑し、その画蹟に啓発されながら、独自の画風を築き上げたことはよく知られている。
水流を伴う紅梅・白梅の画題や二曲一双の左右隻に画材をおさめる構成.."
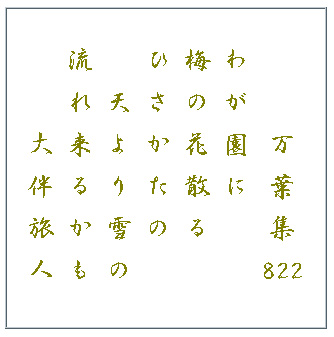
 二月の梅です・・
二月の梅です・・ 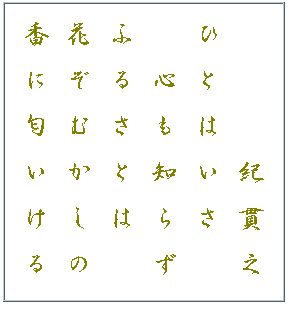
 八重向梅
八重向梅 
 長剣梅鉢
長剣梅鉢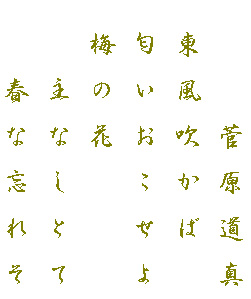

 光琳梅家紋
光琳梅家紋
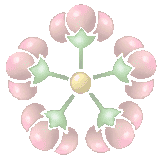


 剣梅鉢
剣梅鉢 



 超有用サイト:
超有用サイト:

